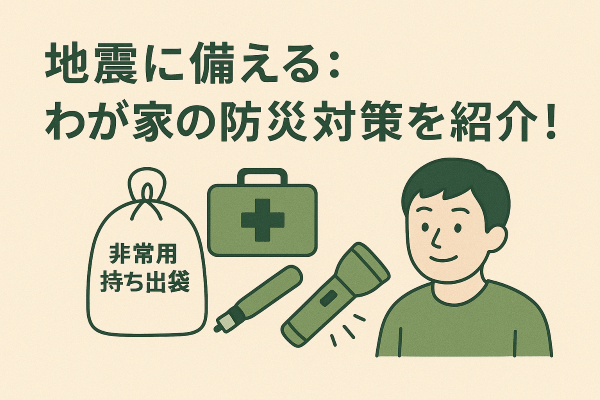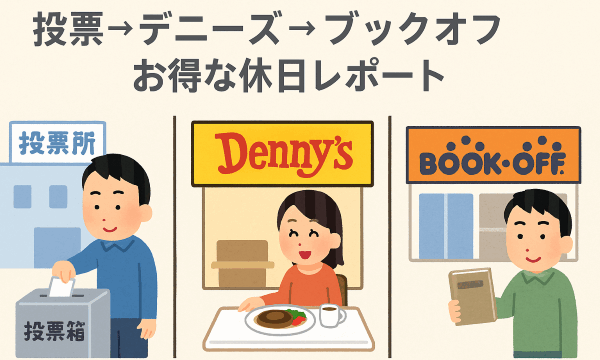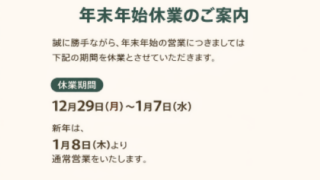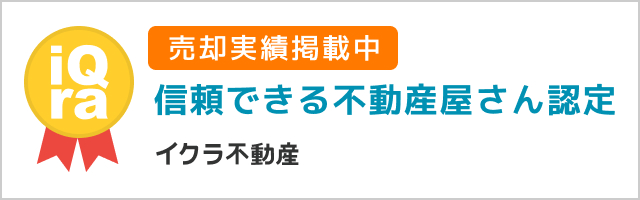地震に備える:わが家の防災対策を紹介します
日本に住んでいる限り、地震は避けられない災害です。特に、南海トラフ地震が注目されていますが、東京都にお住まいの方にとっては「首都直下型地震」も警戒すべき存在です。
内閣府の発表によれば、今後30年以内に発生する確率は約70%とも言われています。
今回は、我が家で実践している地震対策についてご紹介いたします。
1.建物の耐震補強を実施
最初に取り組んだのは、建物の耐震性の見直しです。
旧耐震基準とは?
1981年(昭和56年)5月31日以前に建築確認を受けた建物は「旧耐震基準」で建てられており、現在の耐震基準に比べると地震に対する強度が不足している可能性があります。
旧耐震の建物だからといって必ず倒壊するわけではありませんが、我が家ではリフォームのタイミングに合わせて、耐震診断と耐震補強工事を行いました。
実施した工事内容
-
基礎の補強(ひび割れ部分の補修)
-
壁の補強(筋交いや構造用合板の追加)
-
柱の接合部に制震金具を設置
特に、地震エネルギーを吸収する制震金具の効果に期待しています。
費用とメリット
-
リフォーム工事に加えて、耐震補強費用は+約100万円程度
(耐震補強工事だけ単独で行うと、もう少しかかると思います。) -
耐震基準適合証明書が発行され、住宅ローン控除や登録免許税の軽減などの税制優遇も受けられました
なお、私の住む三鷹市には耐震診断、補強工事等に関する補助制度がありましたが、工事後に相談したため利用することができませんでした。
必ず事前に自治体へ相談されることをおすすめします。
2.ハザードマップと地域危険度をチェック
東京都では、「地震に対する地域危険度調査」が公表されています。これは町丁目ごとに以下の4項目を5段階で評価したものです。
-
建物倒壊危険度:建物の損壊リスク
-
火災危険度:火災の延焼リスク
-
災害時活動困難係数:避難や救助のしやすさ
-
総合危険度:上記3項目の総合評価
また、自治体が作成するハザードマップでは、地震時の「避難所」や「危険箇所」なども確認できます。住んでいる地域のリスクを知ることは、防災対策の第一歩です。
3.日常の備え:家具の固定・飛散防止・備蓄食料
備えのポイント
-
家具の固定:転倒防止器具やL字金具で固定
-
ガラスの飛散防止:窓やガラス棚に飛散防止フィルムを貼付
-
備蓄食品・水:最低3日、可能であれば1週間分を目安に確保
大規模災害では支援物資の到着が遅れることもあります。コンビニやスーパーも機能しない可能性があるため、自助の備えがとても重要です。
まとめ
地震対策は「やるべき」と分かっていても、どうしても後回しになりがちです。
しかし、いざという時に自分や家族の命を守るのは、事前の準備次第。
-
建物の耐震性を確認・補強する
-
ハザードマップで地域のリスクを知る
-
家具の固定や備蓄など、日常の備えを怠らない
こうした一つひとつの対策が、大きな安心につながります。
ぜひ、ご自身のご家庭でも地震対策を見直してみてください!