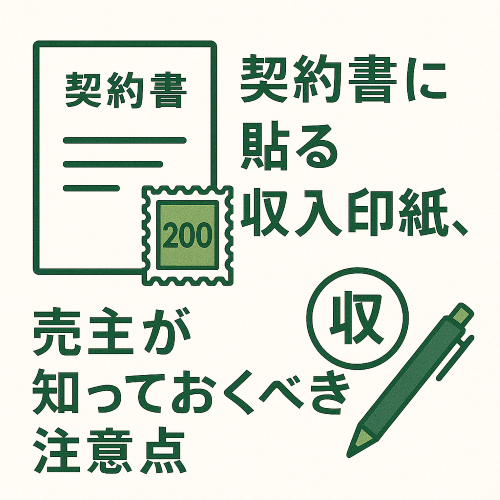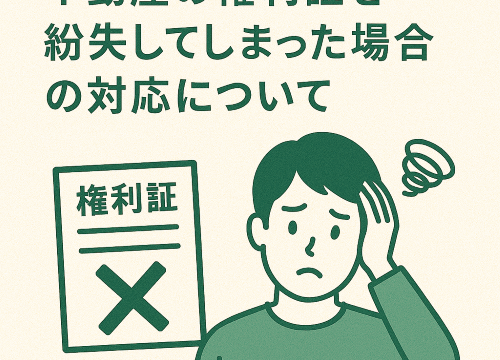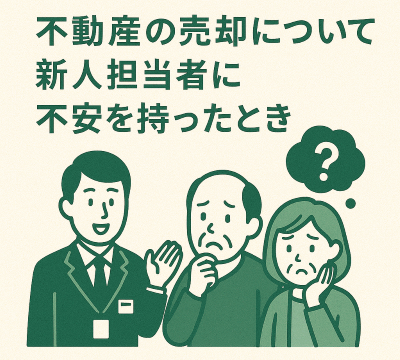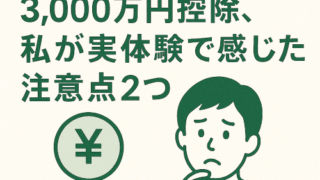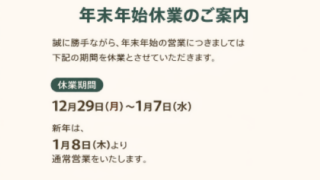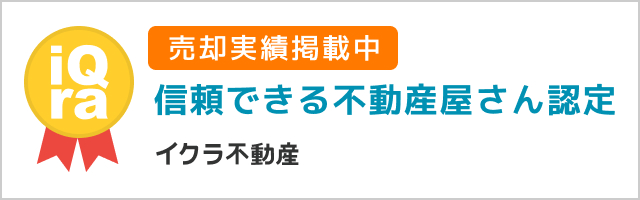印紙のルールと作成部数の関係
不動産の売買契約書には、「収入印紙」を貼付する必要があることをご存じでしょうか?
この印紙代は、契約金額に応じて金額が決まる「税金」であり、契約書は「課税文書」にあたるために必要となるものです。
不動産売買契約書を2通作成する場合は、それぞれの契約書が「正本」としての効力を持つため、それぞれに印紙を貼付する必要があります。つまり、1通につき1枚の印紙代がかかるのです。
しかし、1通しか作成しない場合はどうでしょう?
高額取引ほど重要になる「印紙代の取り決め」
印紙代の負担は、一般的には以下のような取り扱いとなります。
通常は「折半」が多い
契約書の原本は、住宅ローンの手続きなどの関係で買主が保管するケースが多く、売主はその写しを保管します。
このような場合は、印紙代を売主・買主で折半するのが一般的です。
ただし交渉の余地はある
売主としては「なるべく手元に現金を残したい」という思いから、「原本を保管する買主が全額負担すべき」と考える場合もあります。
一方で買主からすれば、「折半なら本来かかる印紙代の半額で済むのに…」という気持ちもあるため、印紙代が交渉材料になることもあります。
印紙税額は、契約金額に応じて変わります。
たとえば
- 売買価格が1,000万円超~5,000万円以下 → 印紙税額は1万円
- 売買価格が5,000万円超~1億円以下 → 印紙税額は3万円
- 売買価格が1億円超~5億円以下 → 印紙税額は6万円
こうなると、ちょっとした金額では済みません。
実際に「誰が負担するか」を後回しにしていると、本来スムーズに進むはずの他の条件交渉に影響を及ぼすケースもあるのです。
まとめ
「たった数万円の話」と思われるかもしれませんが、お金に関することは感情に関わります。
印紙代のような細かな項目ほど、早い段階でしっかり話し合っておくことが大切です。
あとから交渉に持ち込むと、お互いに譲れることも譲れなくなり、結果として関係がギクシャクする原因になりかねません。
些細なことだからこそ、先手を打って、スムーズな契約を進めていくことが大事となります。